労働安全衛生法第71条の2に基づく快適職場づくりー安全委員会での作業帽子選定ポイントー
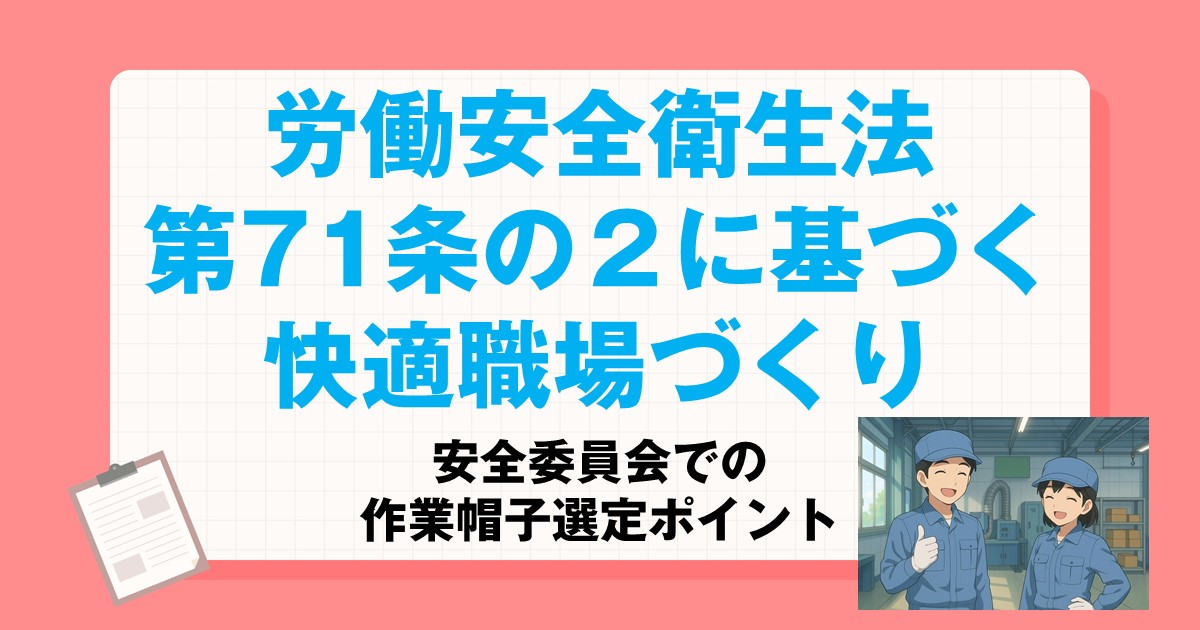
製造業・運送業など、工場や倉庫で働く方たちにとって、作業帽子やヘルメットなどの保護具は欠かせないアイテムです。一見するとただ「頭を覆うための道具」ですが、実は労働安全衛生法の理念や、事業者が追う災害防止・安全配慮義務と密接に関係してきます。
労働災害の発生要因を見ると、「転倒」「飛来・落下物」「軽微な衝突」など、頭部を守ることで被害を軽減できる事故は数多くあります。ヘルメットが必要な場面はもちろん、屋内作業や軽作業時での作業帽子の役割が注目されつつあります。
さらに近年では、人手不足、熱中症への対策として、単なる安全対策にとどまらず「快適に働くことが出来る環境づくり」が重要視されるようになっています。そして労働安全衛生法における快適職場づくりへの考慮も必要となります。
この記事では労働安全衛生法第71条の2を取り上げ、さらには事業者に設置が求められる(設置要件あり)、安全委員会での作業帽子に対する取組みもご提案していきます。
目次:
1.労働安全衛生法第71条の2と快適職場環境の関係
2.安全委員会で作業帽子を取り上げることは必要?
3.安全委員会で考える作業帽子選定のポイント
4.事例から学ぶ作業帽子選びの成功と失敗
5.作業帽子がもたらすメリット
6.まとめ
1.労働安全衛生法第71条の2と快適職場環境の関係
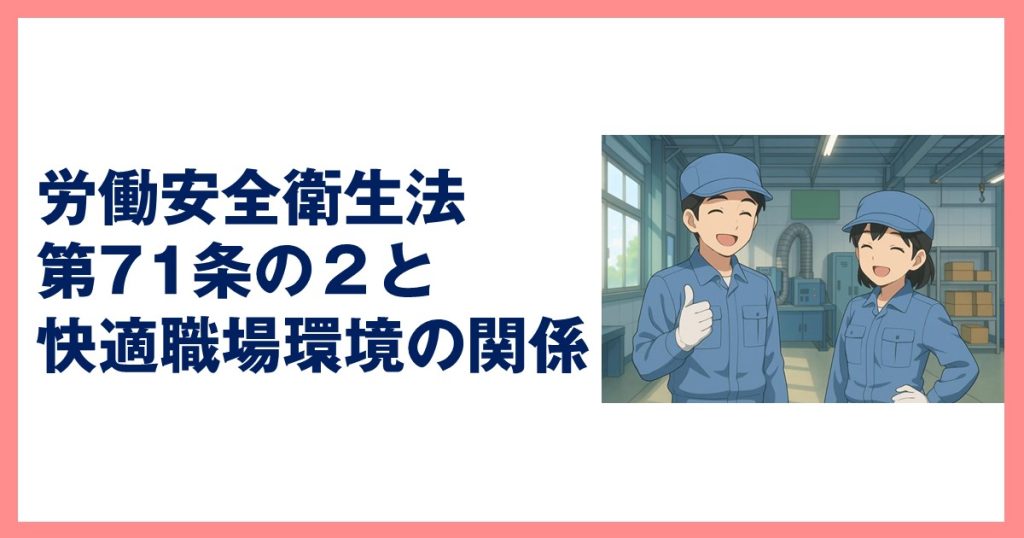
労働安全衛生法とは、「労働者が職場で安全・健康に働くことが出来るように」職場環境を快適にする目的で制定された法律です。1972年6月に労働基準法から分離独立しました。制定後も随時改正が行われています。2025年1月1日の改正においては、労働安全衛生関係の一部手続きの電子申請が義務化されるなど、随時変化が発生していきます。改正内容を常に入手し、理解を深めていくことが重要です。
※労働安全衛生法は、略して安衛法とも呼ばれますが、似たような言葉として「安衛則」があります。安衛則は労働安全衛生規則を略した言葉です。こちらは、厚生労働省が「労働安全衛生法」に基づいて制定した、労働環境の安全や衛生などの確保を目的とした省令です。法律と省令(規則)の違いは、法的拘束力の違いなどが挙げられますが、大変専門的な内容となりますので、今回の記事では割愛させていただきます。
※この記事も合わせてお読みください。
製造業の安全担当者が知っておきたい!熱中症対策×作業帽子の最新事情
労働安全衛生法は全12章、123条で構成されています。
その中で今回は、「第7章の2」に掲載されている、第71条の2を取り上げていきます。
労働安全衛生法第71条の2では、事業者に対して「快適な職場環境を形成するように努めなければいけない」旨が定められています。
では、快適な職場環境とは?という疑問が出てきますが、こちらについては厚生労働大臣により【快適職場指針】が1992年に公表されています。
そちらによると、目指すものとして「仕事による疲労やストレスを感じることの少ない、働きやすい職場づくり」とされています。
上記では4つの視点による措置が望ましいとしています。
① 作業環境への視点
不快と感じることがない、快適な状態に維持管理するための措置。空気の汚れ、臭気、温度を適切に維持管理する、視環境、音環境、作業空間を確保する、など。
② 作業方法への視点
作業者の心身の負担を軽減するため、機械設備の導入、作業しやすい配慮など。
③ 疲労回復への視点
作業者の疲労やストレスを効果的に回復するための休憩室等を設置・整備するなど。
④ 職場生活支援への視点
食堂や給湯設備の確保、洗面所・トイレなど、職場生活で必要となる施設等を清潔で使いやすい状態にしておくなど。
参考・引用:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo11_1.html
ここで触れておきたいポイントは、労働安全衛生法第71条の2は「努力義務」であることです。必須の義務ではなく、最低限の安全管理を行えば法的に問題はありません。
しかし、努力義務だからこそ、事業者や安全委員会(もしくは衛生委員会)の工夫次第で、安全+快適な職場を実現することができます。
昨今、求人を出しても応募が来ないという声は多くの企業から聞かれます。人手不足倒産も残念ながら多発しています。
そのような中、少しの気配り、少しの工夫で貴社の魅力をアップし、求職者の方に「この会社で、この現場で働きたい」と思っていただけます。
この「少しの気配り・少しの工夫」のための一つの施策として「作業帽子の適切な選定」を次トピックからご紹介してまいります。
2.安全委員会で作業帽子を取り上げることは必要?

事業者が事業場の安全に関する重要事項を話し合う場として、安全委員会があります。
※労働安全衛生法第17条で定義されています。設置要件、構成員、開催頻度などは下記のWEBサイトからご覧いただけます。
参考:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo41_1.html
衛生委員会、安全衛生委員会など、他の会議体もございます。
また、業種、規模(常時使用する労働者数)などによって、設置義務がない事業者もあります。労働者が50人未満の場合、このような委員会の設置義務はありませんが、そのような場合でも労働者に安全、衛生に関する機会は設けなければなりません(安衛則23条の2)。
「うちの会社では安全委員会は開催していないから関係ないかな」という場合でも、ぜひお読みください。
安全委員会で話し合われるべき事項
安全委員会では、事業者に対して下記についての意見を述べなければならない、とされています。
逆に言うと、事業者は安全委員会に意見を述べさせるために安全委員会を設けなければいけません。
【1】 労働者の危険を防止するための基本となるべく対策に関すること
【2】 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に関わるものに関すること
【3】 上記2つ以外で、労働者の危険の防止に関する重要事項
安全委員会は毎月1回以上開催することとされています(安衛則23条)。様々な事柄が話し合われる形となりますし、残念ながら労働災害が発生した月などは、考えるべきこと、決定すべきことが多く出てきます。
このような委員会の中で、普段から身に着けている作業帽子についての話題が上がることはあまりないかもしれません。
ただ、それでも安全委員会の中で作業帽子を取り上げるべき理由、ございます。
安全委員会で作業帽子を取り上げる理由
まず、
【1】 労働者の危険を防止するための基本となるべく対策に関すること
と作業帽子との関連を考えてみます。
作業帽子は、ユニフォームの単なる1アイテムではありません。頭部を衝撃から守る、暑さを軽減する、などの保護アイテムでもあります。
頭を守る保護具としてはヘルメットを最初にイメージしますが、実は作業帽子も大切な保護アイテムなのです。
労働災害の中で、転倒を原因とする事故は多くございます。そのような中、作業帽子も対策の一つとなります。
※下記記事も合わせてお読みください。
「転倒=大ケガ」を防ぐ!作業現場で使える”かぶる労災対策”とは?ーヘルメットを被るほどではないけれど頭部保護が必要な現場でー
ただし、どのような作業帽子でも良いわけではありません。
転倒対策にも活用できる作業帽子なのか、などを検討することも大切です。
また、作業帽子の快適性が不十分だと、作業者の着帽率が下がり、結果、安全ルールが守られなくなることが考えられます。
また、
【2】 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に関わるものに関すること
にも関係します。
再発防止対策を考える上で、直接的な原因に対する対策だけでは不十分な場合があります。日常の安全ルールの遵守の上で成り立つ対策であれば、【1】の検討も必要だからです。
事業場、作業現場で使用する作業帽子について、現状のままで良いのか(深く考えずにユニフォームのひとつとして従来の帽子を使い続けて良いのか)を安全委員会で話し合うこと、実は大変重要です。
安全で快適な作業帽子を導入することで、貴社で働く方たちの満足度向上にも繋がります。
作業帽子は見落とされがちな項目になるのですが、重要なテーマとして、安全委員会で積極的に検討する価値、ございます。
ぜひ貴社の安全委員会で取り上げてみてください。
3.安全委員会で考える作業帽子選定のポイント

では、安全委員会で「自社に最適な」作業帽子を選定する、と決まった場合、どのようなポイントを基に考えていけばよいのか、ご紹介していきます。
ポイント① 安全性(保護性能)
まずおさえるべきは安全性です。
作業帽子にどこまでの安全性を求めるのか、を考えていくことも必要ですが、どのような現場で、どのような事象に対応したいのか、をまず考えましょう。
高所での作業で落下の危険がある、または飛来・落下物の危険がある作業現場では、作業帽子よりもヘルメット(保護具)が必要です。
ただ、軽作業や屋内作業(倉庫作業)で、いわゆるヒヤリ・ハットに備える場合では、衝撃吸収材などが入った作業帽子が有効となります。
※参考に下記もお読みください。
職場に潜むヒヤリ・ハットから頭を守れ 製造現場の「滑る」「転ぶ」「ぶつける」に備える作業帽子
作業内容に応じた適切な保護性能を検討し、過剰でも不十分でもないバランスを見極めていくことが重要です。
ポイント② 快適性(通気性・遮熱・軽量性)
労働安全衛生法第71条の趣旨に直結するポイントです。
「作業環境への視点」による措置を検討するうえで、作業帽子に下記の観点を取り入れてみてください。
●熱中症対策として通気性や遮熱性能が必須
●吸汗速乾素材が使用されていれば汗による不快感が軽減できる
●軽量であれば首や肩の負担を減らすことが出来る
被っていて快適な作業帽子であれば、自然と着帽率が上がります。結果、安全性の確保にもつながります。
※下記も参考にお読みください。
夏の現場を快適に!涼しさと通気性で選ぶ作業帽子 メッシュ素材がおすすめ
作業帽子は、カタログなどでは分からない「着用感」を大量購入前に知ることも大切です。有償サンプルなどを取り寄せ、現場で試し、現場の声を聞くこともお勧めします。
ポイント③ 衛生管理(抗菌)
作業帽子は長時間着用し、肌に触れるものですので衛生面も無視できません。
●洗い替え用のスペアも用意する
●抗菌・防臭加工がされている作業帽子を選ぶ
●個人用・共用用での管理ルールの違い
などを考慮します。
安全委員会で管理ルールなども明確にしていくことで、働く人の健康リスクを低減できます。
※ジュトクの作業帽子では、洗濯は「手洗い」、乾燥は「日陰干し」を推奨しております。また、汗止め部分には抗菌・防臭効果素材を使用しております。(対象製品などはお問合せください)
ポイント④ デザイン性と心理的快適さ
「かぶりたくない」と思われてしまう作業帽子では、どんなに安全性が高くても着帽率は下がってしまいます。
●性別問わずフィットするデザイン、または性別によって好まれるデザイン
●配色で部署・役割の識別が可能な作業帽子
●現場の士気を高めることが出来るスタイリッシュなデザイン
などを考慮します。
※下記も参考にお読みください。
ロングヘア―の方向け作業帽子「崩れない・蒸れない・かわいい」三拍子そろった、夏も快適に働ける帽子の選び方とは?
作業帽子はネイビーが人気の理由とは?現場で選ばれる色とおすすめ帽子紹介
工場見学の印象をアップさせる!作業帽子のカラーバリエーション活用術
心理的快適さは、作業帽子の着用習慣の定着に直結します。
以上、4つのポイントをベースに、安全委員会で貴社に最適な作業帽子を検討することをお勧めいたします。
4.事例から学ぶ作業帽子選びの成功と失敗

前トピックでご紹介したポイントを考慮せずに作業帽子を選ぶと、どのような状況になっていくのか、シミュレーションしてみたいと思います。
物語として表現してみました。
失敗例を知ることで、成功するための方法をぜひみなさんで考えてみてください。
かぶられなくなった作業帽子の教訓
愛知県某地域にある自動車部品メーカーのA社。その月の安全委員会はいつも以上に熱を帯びていた。
「もっと頭部の保護を強化できないか?」
ある委員がそう口にしたことが発端だった。小さな部品の落下事故や、ちょっとした接触によるケガが続き、「通常の作業帽子では心もとない」という意見が強まっていたのだ。
そこで導入されたのが、“インナーキャップ”だった。普段使っている作業帽子の内側に、少し硬めの素材でできた保護用カバーを装着し、作業者全員に着用を義務づける。安全委員会は胸を張った。
「これで頭部の安全は格段に向上するはずだ」
しかし、現場に下ろしてみると状況は違った。普段使っている作業帽子は、通気性などは加味されていない、ユニフォームと共に導入した、いわば、「普通のキャップ」。夏場、そこに硬めの素材のインナーキャップを装着すると、かなりの熱気がこもるようになってしまったのだった。
額から滴る汗が視界を曇らせ、耳の後ろには蒸れによるかぶれができる人まで出た。
「これじゃあ、かえって仕事に集中できない」
そんな声が現場で広がり、ついにはインナーキャップを外すだけでなく、帽子そのものをかぶらなくなる作業者まで出てきた。
安全委員会が描いた「安全性の向上」は、逆に「安全意識の低下」を招いてしまったのだ。机上では完璧に思えた対策が、実際の作業環境では大きな負担になっていた。
その失敗は、委員たちに重くのしかかった。
「安全とは、ルールを押し付けることではない。現場で続けられる形でなければ意味がない」
そう痛感した彼らは、作業者と共に改めて“かぶりたくなる帽子”を探し始めるのだった。
失敗例から学ぶ教訓
上記はあくまで架空のストーリーです。
頭部の安全を確保するために、現在の帽子にインナーキャップを装着する、そのアイディアはとてもよいものです。
しかし、帽子を被ったときの「快適さ」に目が届いていなかったことが、この物語の上での重要ポイントです。
安全性を打ち出すときに、「現場目線」で議論を行うことが出来るか、が重要で、成功への道となります。
いくら安全性が高まるアイテムであったとしても、着用してストレスを感じてしまうようだと、作業者は「なるべく使いたくない」という気持ちに陥ってしまいます。
そして、近い時期に「限界」が訪れ、結果、安全性が低下する事態にも至ります。
現場目線を得る、つまり、現場の声をヒアリングすることが大切です。どのような作業帽子であれば、「こうありたい」結果を得られるのか。そこをぜひ安全委員会で議論してください。
5.作業帽子がもたらすメリット

最後に、作業帽子がもたらすメリットにはどのようなものがあるのかご紹介します。
適切な作業帽子を導入することで、多方面に効果をもたらします。
例えば下記が挙げられます。
●作業帽子の着帽率が向上する
→「必ず作業帽子を被る」などの安全ルールが徹底されていきます。
●作業効率が改善する
→快適な頭部環境が作業者の集中力を支え、結果、作業効率が改善します。
●職場への満足度が向上する
→快適な作業環境は、そこで働く人たちの満足につながり、企業への信頼感が高まり、離職防止にもつながります。
これらは、労働安全衛生法第71条が掲げる「快適職場環境形成」へも繋がる内容となります。
6.まとめ
安全委員会から始める快適な職場環境作りをテーマとしてご説明してきました。
労働安全衛生法第71条は努力義務ですが、安全委員会の取り組み方次第で、企業、そしてそこで働く人たちに向けて大きな成果を上げられます。
貴社環境にとっての適切な作業帽子を選定していただくことで、「安全の確保」、「快適な職場作り」、「働く人のモチベーション向上」につながります。
ぜひ安全委員会において「現場の声」を反映し、作業帽子選定を行う取組み、チャレンジしてはいかがでしょうか?
単なる「安全用品の支給」ではなく、職場全体の安全・快適に向けた文化を育む第一歩となるでしょう。
日本の作業現場を快適にしたい、そうすることで皆さまの課題解決のお役に立ちたい、そんな想いを持ち、作業帽子を制作しております。
お困りごとなどございましたら、ぜひご相談いただければと思います。
お問い合わせはこちらまで。
